院長駄文
Doctor column
第1回 習慣について ~生活習慣病を克服するには?~
2025年10月1日(水)
開院して間もなく5ヶ月になります。
おかげさまで、国見ヶ丘をはじめ、様々な地域から想定を上回る患者さんに御来院頂いており、望外の喜びを感じています。
「生活習慣病を改善したい」という気持ちでこのクリニックを開院したのですが、「生活習慣病を改善する」ことは、「生活習慣を改善する」ことと、かなり近いです。インスリン分泌能力の低下した糖尿病や、一部の高LDL-コレステロール血症などは、日々の食事や運動に気をつけても、なかなか改善しないこともありますが、カロリー摂取過剰や運動不足に由来する、2型糖尿病、本態性高血圧、脂質異常症、肥満症は、生活習慣と密接に結びついています。
なので、今回は、「習慣」について日々の診療で感じていることを書いてみます。
*******************
心が変われば態度が変わる。
態度が変われば行動が変わる。
行動が変われば習慣が変わる。
習慣が変われば人格が変わる。
人格が変われば運命が変わる。
運命が変われば人生が変わる。
*******************
現役時代は捕手、26年の現役生活、657本のホームランを放ち、南海ホークス、ヤクルトスワローズ、阪神タイガーズ、楽天ゴールデンイーグルスなどで監督をされた、「ノムさん」こと、故・野村克也監督の書籍で目に留まった言葉です。もともとは、ヒンズー教に由来するようですが、深い感銘を受けました。実は、私が患者さんと接するときも、同じようなことを考えていて、生活習慣の本質を射抜いている一文だと思います。
まず、健診結果などを見て、「変わりたい」という気持ちを持って、クリニックを訪問するところが出発点になります。健診結果を見ても、「変わりたい」という気持ちが弱ければ、クリニックを訪問せずに日々の仕事や生活を過ごすことになり、そういう方々も数多くいらっしゃるでしょう。ですので、クリニックを訪問した時点で、何かしらの変化を受け入れる心の準備ができているのだと思います。心の変化が出発点で、「きっかけ」そのものであることに、異論の余地はないでしょう。
これまで私が診察室で出逢った患者さんの話を聴く限りでは、人間は、一般的には、年齢を重ねると変化を好まなくなるようです。自分を変えるには、多くのエネルギーが必要になりますが、そういった労力が億劫になり、何かしら理由をつけて、「今のままで良い」と判断する人も一定数いらっしゃいます。
私は、「今のままで良い」には一長一短があると思います。やりたいことが特にないのであれば、文字通り「今のままで良い」かもしれません。ただ、やりたいことがある場合には、少しでも今の自分に、将来の自分に他の可能性を感じているのなら、ちょっとした変化を受け入れることで、健康寿命が延びて、まわりにも迷惑をかけずに、人生をもっと謳歌することができるかもしれません。
ただ、日常生活を大きく変え過ぎたり、頑張り過ぎたりすると、それがストレスになって、なかなか長続きしません。生活習慣病は、(極端に言えば、死ぬまで)ずっと付き合っていくものなので、無理は禁物です。まずは一箇所、1つだけで良いので、どこか1つを少しだけ変えるのがオススメです。夕食後・寝る前の間食をやめるとか、1日20分のウォーキングを始めるとか、自宅で血圧を測って記録し始めるとか、続けられそうな範囲でこれまでと違うことをするように提案することが多いです。そして、自分の中で変更したものが新しい「習慣」として定着したら、また新しく1つ他のことを変えてみるのです。
19世紀のフランスに、ラヴェッソン(Jean Gaspard Félix Ravaisson-Mollien, 1813-1900)という哲学者がいます。『習慣論(De l'habitude)』という著作(岩波文庫に翻訳がありますが、内容的には非常に凝縮されていて読むのが大変な本)を残しているのですが、その習慣に関する主張の数々は、野村監督の書籍からの引用と、内容的にはほとんど変わらないと思います。私なりに、生活習慣病の文脈で読み解いてみました。
まず、変わりたいという気持ちがあって、そこは自分の意志次第で、自由と裁量があり、本人の決断に任されています。未来への希望があり、これまでの自分を省みる人であれば、わずかであっても変わる余地は残されています。ここはまさに「こころ」の持ちよう次第です。
一方で、古来「生老病死」という表現もあるように、生まれたらいずれ老いて、病気になって、死ぬことは自然の摂理で、避けられない運命です。何もしなければ、身体機能は少しずつ衰えていくのですが、脳梗塞で半身麻痺になった場合には、できることも限られます。なので、人間として生きていく限り「からだ」の制約が生じるのは必然です。
習慣は、「こころ」と「からだ」、これら2つの合力で成り立っている、というのが、私の考えるラヴェッソン流の解釈です。習慣は、「こころの状態」と「からだの状態」という、ときに合致してときに対立する二者をつなぎ、「こころ」と「からだ」両者の特徴を併せ持っています。
「毎日3000歩ウォーキングをする」と新しく決めたとき、ずっと意志の力で行動を続けることは大変です。エネルギーがいりますし、疲労感も半端ないです。ところが、習慣になってしまえば、習慣としてからだに馴染んでしまえば、それほど努力はいらないので、頑張らずに、継続しやすくなります。むしろ、からだに合うもの、からだに違和感を感じさせないものが習慣になる、という説明のほうが正しいでしょう。
一方で、「毎日3000歩ウォーキングをする」という習慣は、ただの習慣ではありません。そこには、「体重を減らしたい」とか「筋力を維持したい」とか「血糖値を良くしたい」といった、「変わりたい」という願望が潜んでいます。人間はいつかは老いて病気になって死ぬし、それは自然の摂理で、避けられない運命だけれども、死ぬまでどう過ごすかは個人の自由です。だから、どんな習慣を形成するかには、その人の人柄や価値観、逼迫したニーズ、こころが色濃く反映されます。
習慣をじっと見つめれば、どういう人生にしたいのか、どういう「生きがい」を持って自分らしく生きようとしているのかも分かります。習慣は、「こころ」と「からだ」という(パッと見ると対立する)二者の間で、あるときは「こころ」に傾いたり、あるときは「からだ」に寄り添ったり、様々な揺れ動きを経験しながら行きつ戻りつして、両者を一つにまとめて、落ち着くところに落ち着くのだと思います。
新しい習慣を身につけたとしても、果たして、病気を予防できるかどうかは誰にも分かりません。ただ、たばこを吸わなければ、肺癌になる確率は下がります。歯医者さんに定期的に通院してメンテナンスしてもらっていれば、虫歯や歯周病の重症化を避けられます。「人事を尽くして天命を待つ」という格言もありますが、そういった心構えで自分の習慣を見つめ直すことが、生活習慣病を克服する王道ではないかと感じています。
【まとめ】
・生活習慣病の改善は「生活習慣の改善」から始まる。
・出発点は「変わりたい」という心の変化。
・長続きしない無理な努力よりも、小さな習慣の積み重ねが重要。
例:間食を控える・毎日少し歩く など
・習慣は「心」と「身体」の両方の働きで成り立つ。
・習慣を整えることで、健康寿命を延ばし、自分らしい人生を実現できる。
・習慣は自分そのものである。
おかげさまで、国見ヶ丘をはじめ、様々な地域から想定を上回る患者さんに御来院頂いており、望外の喜びを感じています。
「生活習慣病を改善したい」という気持ちでこのクリニックを開院したのですが、「生活習慣病を改善する」ことは、「生活習慣を改善する」ことと、かなり近いです。インスリン分泌能力の低下した糖尿病や、一部の高LDL-コレステロール血症などは、日々の食事や運動に気をつけても、なかなか改善しないこともありますが、カロリー摂取過剰や運動不足に由来する、2型糖尿病、本態性高血圧、脂質異常症、肥満症は、生活習慣と密接に結びついています。
なので、今回は、「習慣」について日々の診療で感じていることを書いてみます。
*******************
心が変われば態度が変わる。
態度が変われば行動が変わる。
行動が変われば習慣が変わる。
習慣が変われば人格が変わる。
人格が変われば運命が変わる。
運命が変われば人生が変わる。
(野村克也著『野村ノート』より)
*******************
現役時代は捕手、26年の現役生活、657本のホームランを放ち、南海ホークス、ヤクルトスワローズ、阪神タイガーズ、楽天ゴールデンイーグルスなどで監督をされた、「ノムさん」こと、故・野村克也監督の書籍で目に留まった言葉です。もともとは、ヒンズー教に由来するようですが、深い感銘を受けました。実は、私が患者さんと接するときも、同じようなことを考えていて、生活習慣の本質を射抜いている一文だと思います。
まず、健診結果などを見て、「変わりたい」という気持ちを持って、クリニックを訪問するところが出発点になります。健診結果を見ても、「変わりたい」という気持ちが弱ければ、クリニックを訪問せずに日々の仕事や生活を過ごすことになり、そういう方々も数多くいらっしゃるでしょう。ですので、クリニックを訪問した時点で、何かしらの変化を受け入れる心の準備ができているのだと思います。心の変化が出発点で、「きっかけ」そのものであることに、異論の余地はないでしょう。
これまで私が診察室で出逢った患者さんの話を聴く限りでは、人間は、一般的には、年齢を重ねると変化を好まなくなるようです。自分を変えるには、多くのエネルギーが必要になりますが、そういった労力が億劫になり、何かしら理由をつけて、「今のままで良い」と判断する人も一定数いらっしゃいます。
私は、「今のままで良い」には一長一短があると思います。やりたいことが特にないのであれば、文字通り「今のままで良い」かもしれません。ただ、やりたいことがある場合には、少しでも今の自分に、将来の自分に他の可能性を感じているのなら、ちょっとした変化を受け入れることで、健康寿命が延びて、まわりにも迷惑をかけずに、人生をもっと謳歌することができるかもしれません。
ただ、日常生活を大きく変え過ぎたり、頑張り過ぎたりすると、それがストレスになって、なかなか長続きしません。生活習慣病は、(極端に言えば、死ぬまで)ずっと付き合っていくものなので、無理は禁物です。まずは一箇所、1つだけで良いので、どこか1つを少しだけ変えるのがオススメです。夕食後・寝る前の間食をやめるとか、1日20分のウォーキングを始めるとか、自宅で血圧を測って記録し始めるとか、続けられそうな範囲でこれまでと違うことをするように提案することが多いです。そして、自分の中で変更したものが新しい「習慣」として定着したら、また新しく1つ他のことを変えてみるのです。
19世紀のフランスに、ラヴェッソン(Jean Gaspard Félix Ravaisson-Mollien, 1813-1900)という哲学者がいます。『習慣論(De l'habitude)』という著作(岩波文庫に翻訳がありますが、内容的には非常に凝縮されていて読むのが大変な本)を残しているのですが、その習慣に関する主張の数々は、野村監督の書籍からの引用と、内容的にはほとんど変わらないと思います。私なりに、生活習慣病の文脈で読み解いてみました。
まず、変わりたいという気持ちがあって、そこは自分の意志次第で、自由と裁量があり、本人の決断に任されています。未来への希望があり、これまでの自分を省みる人であれば、わずかであっても変わる余地は残されています。ここはまさに「こころ」の持ちよう次第です。
一方で、古来「生老病死」という表現もあるように、生まれたらいずれ老いて、病気になって、死ぬことは自然の摂理で、避けられない運命です。何もしなければ、身体機能は少しずつ衰えていくのですが、脳梗塞で半身麻痺になった場合には、できることも限られます。なので、人間として生きていく限り「からだ」の制約が生じるのは必然です。
習慣は、「こころ」と「からだ」、これら2つの合力で成り立っている、というのが、私の考えるラヴェッソン流の解釈です。習慣は、「こころの状態」と「からだの状態」という、ときに合致してときに対立する二者をつなぎ、「こころ」と「からだ」両者の特徴を併せ持っています。
「毎日3000歩ウォーキングをする」と新しく決めたとき、ずっと意志の力で行動を続けることは大変です。エネルギーがいりますし、疲労感も半端ないです。ところが、習慣になってしまえば、習慣としてからだに馴染んでしまえば、それほど努力はいらないので、頑張らずに、継続しやすくなります。むしろ、からだに合うもの、からだに違和感を感じさせないものが習慣になる、という説明のほうが正しいでしょう。
一方で、「毎日3000歩ウォーキングをする」という習慣は、ただの習慣ではありません。そこには、「体重を減らしたい」とか「筋力を維持したい」とか「血糖値を良くしたい」といった、「変わりたい」という願望が潜んでいます。人間はいつかは老いて病気になって死ぬし、それは自然の摂理で、避けられない運命だけれども、死ぬまでどう過ごすかは個人の自由です。だから、どんな習慣を形成するかには、その人の人柄や価値観、逼迫したニーズ、こころが色濃く反映されます。
習慣をじっと見つめれば、どういう人生にしたいのか、どういう「生きがい」を持って自分らしく生きようとしているのかも分かります。習慣は、「こころ」と「からだ」という(パッと見ると対立する)二者の間で、あるときは「こころ」に傾いたり、あるときは「からだ」に寄り添ったり、様々な揺れ動きを経験しながら行きつ戻りつして、両者を一つにまとめて、落ち着くところに落ち着くのだと思います。
新しい習慣を身につけたとしても、果たして、病気を予防できるかどうかは誰にも分かりません。ただ、たばこを吸わなければ、肺癌になる確率は下がります。歯医者さんに定期的に通院してメンテナンスしてもらっていれば、虫歯や歯周病の重症化を避けられます。「人事を尽くして天命を待つ」という格言もありますが、そういった心構えで自分の習慣を見つめ直すことが、生活習慣病を克服する王道ではないかと感じています。
【まとめ】
・生活習慣病の改善は「生活習慣の改善」から始まる。
・出発点は「変わりたい」という心の変化。
・長続きしない無理な努力よりも、小さな習慣の積み重ねが重要。
例:間食を控える・毎日少し歩く など
・習慣は「心」と「身体」の両方の働きで成り立つ。
・習慣を整えることで、健康寿命を延ばし、自分らしい人生を実現できる。
・習慣は自分そのものである。


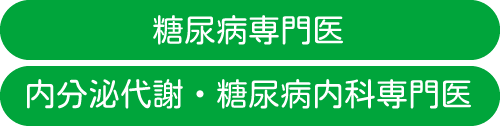

 院長紹介へ戻る
院長紹介へ戻る